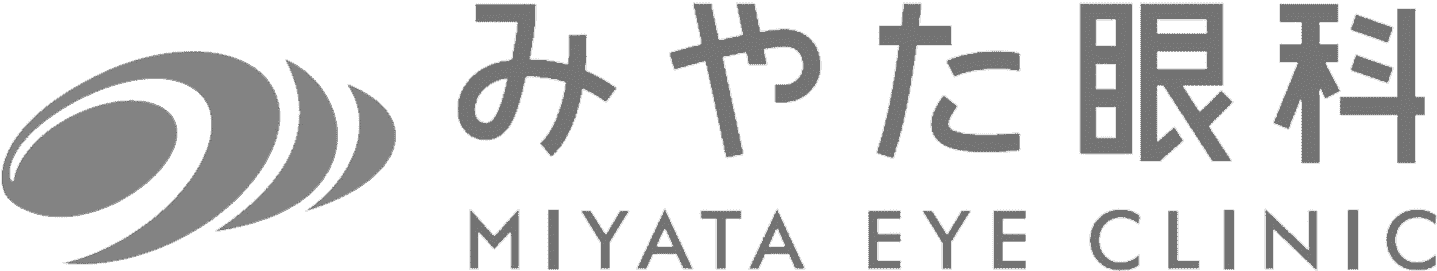視神経乳頭陥凹が大きいと言われた方へ
健康診断や他の眼科で「視神経乳頭の陥凹(くぼみ)が大きいですね」と言われて、心配になっていませんか?
視神経乳頭の陥凹が大きいことは、緑内障の可能性を示すサインの一つですが、必ずしも「陥凹が大きい=緑内障」というわけではありません。
ここでは、視神経乳頭陥凹と緑内障の関係について、分かりやすくご説明します。
「視神経乳頭」とは?
まず、眼の奥には「視神経乳頭(ししんけいにゅうとう)」という部分があります。これは、眼で見た情報を脳に伝えるための神経線維(視神経)が集まって、脳へと向かう”出口”のような場所です。たくさんの神経線維が束になっている、とても大切な部分です。
「視神経乳頭陥凹」とは?
視神経乳頭の中央部分には、もともと生理的な「くぼみ」があります。これを「視神経乳頭陥凹」と呼びます。
このくぼみの大きさや形は、生まれつき個人差があります。近視が強い方などは、もともと陥凹が大きい傾向があることも知られています。
ですから、陥凹が大きいこと自体が、すぐに異常というわけではありません。
なぜ「緑内障」と関係がある?
緑内障は、何らかの原因で視神経が傷つき、視野(見える範囲)が徐々に狭くなっていく病気です。多くの場合、眼圧(眼の硬さ)がその原因の一つと考えられています。
緑内障が進行すると、眼と脳をつなぐ神経線維が少しずつ減っていきます。神経線維が減ると、その”出口”である視神経乳頭のくぼみ(陥凹)が、相対的に大きく見えるようになるのです。
つまり、「視神経乳頭陥凹の拡大」は、緑内障によって視神経がダメージを受けている可能性を示す重要なサインとなります。
検査で何をみているの?
眼底検査
眼の奥(眼底)を直接観察したり、写真を撮ったりして、視神経乳頭の色や形、陥凹の大きさ、神経線維の厚み(リムと呼ばれます)などを確認します。
OCT(光干渉断層計)
眼底に特殊な光を当てて、視神経乳頭やその周りの網膜(カメラでいうフィルムの部分)の断面図を撮影します。これにより、神経線維の厚みを精密に測定し、緑内障による変化がないかを客観的に評価できます。陥凹の大きさだけでなく、神経線維が実際に減っているかどうかが分かります。
視野検査
見える範囲に異常(欠けている部分)がないかを調べます。緑内障の進行度を評価する上で非常に重要な検査です。
これらの検査結果を総合的に判断し、緑内障かどうか、また緑内障の疑い(緑内障予備軍)なのか、あるいは単に生理的な陥凹が大きいだけなのかを診断します。
「陥凹が大きい」と言われたらどうすればいい?
まず、過度に心配しないでください。大切なのは、ご自身の眼の状態を正しく知ることです。
「陥凹が大きい」と指摘された場合は、必ず眼科専門医の診察を受け、精密検査を受けるようにしましょう。
緑内障ではない場合
生理的に陥凹が大きいだけであれば、特に治療の必要はありません。ただし、将来的に緑内障を発症する可能性がゼロではないため、定期的な検診をおすすめします。
緑内障の疑いがある場合
まだ視野異常などはありませんが、将来緑内障に進行するリスクが考えられる状態です。定期的に検査を受け、変化がないか注意深く経過を見ていくことが大切です。
緑内障と診断された場合
緑内障は、早期に発見し、適切な治療(主に眼圧を下げる点眼薬)を開始すれば、多くの場合、進行を遅らせることができます。自覚症状がないからといって放置せず、医師の指示に従って治療と定期検査を続けましょう。
まとめ
視神経乳頭陥凹の大きさは、緑内障を発見するための重要な手がかりです。健康診断などで指摘された方は、ぜひ一度、眼科で詳しい検査を受けてみてください。
当院では、最新の検査機器を用いて正確な診断を行い、お一人おひとりの状態に合わせて丁寧に説明し、最適な治療や経過観察の方針をご提案いたします。
大切な眼の健康を守るために、お気軽にご相談ください。