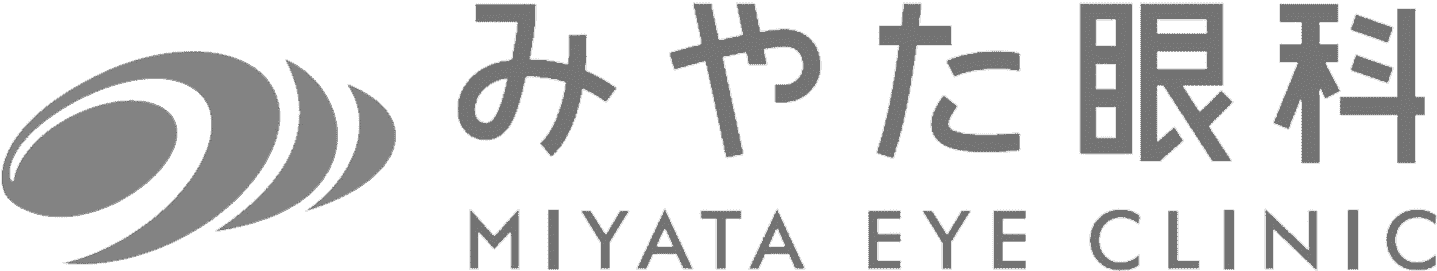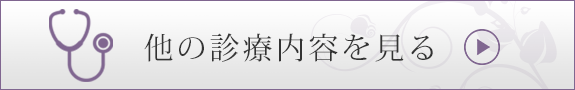乱視
乱視という言葉は、非常になじみのある言葉で、視力に関係するものということは皆さんご存じのようです。
患者さんに『乱視がありますね』とお話しすると、『えっ!本当ですか?』と、とても驚かれる方も居られるし、『そうなんです』と、得々と自分の視力の悪さを説明される方も居られ ます。でも乱視は、視力を測定すれば大抵皆持っているもので、近視や遠視と同じように、目のピントの合い方(屈折)の異常の一つです。決して特別なものではなく本当は乱視のない人の方が珍しいくらいなのです。
要は、その乱視が視力に影響する程の乱視かどうかということなのです。さて、このなじみのある『乱視』について、皆さんはどこまでご存じですか?
「乱視」とは
目に入ってきた光は、カメラでいうところのフィルムにあたる網膜(目の奥のスクリーン)に到達するまでに、角膜(目の前面部分)と水晶体(レンズ)を通り抜けますが、この時に網膜で焦点が合うように屈折されます。この角膜と水晶体の球面形に、ほんのわずかな歪みがあると光の屈折が微妙にずれるためにピントの合い方が悪くなります。この角膜と水晶体の歪みのことを「乱視」と呼びます。角膜の歪みを「角膜乱視」、水晶体の歪みを「水晶体乱視」と呼びます。
一般的に水晶体乱視は頻度も程度もそれほど多いものではないので、普通「乱視」といえば、角膜乱視のことを指します。多くの場合、乱視は生まれつき角膜の形が完全な球面ではないために起こります。いったん乱視になっても、その乱視が一生そのままではありません。乱視は年齢とともに変化するものなのです。
その理由は、角膜は眼球の形の影響を受けますから、若い時に乱視がなくても、長年のまぶたからの圧迫や、眼球をキョロキョロ動かす筋肉の張力によって眼球の形がわずかに変化して、角膜乱視が発生するとも言われています。また若い時に乱視があってもこの眼球の変化で丁度良く乱視がなくなる場合もあります。
後天的に、目の怪我や手術後の合併症、まぶたの圧力による角膜への影響、角膜瘢痕、円錐角膜などの特定の眼疾患によって起こることもあります。また、遺伝的な要因が関連することもあります。
乱視の症状
乱視があると、以下のような症状が現れることがあります。
・距離に関係なくピントが合いにくく、視界がぼやけたり歪む。
・物が二重、三重にブレて見える。
・特に線や文字などがダブって見える。
・夜間の見えにくさ。明るい光からのまぶしさが増加したり、対向車のライトなどがギラギラと眩しく感じたり、にじんで見える。
・目の疲れや不快感(眼精疲労)
・はっきり見るためにまばたきが増える
・ピントを合わせようと目が無理をするため、疲れやすい。
・頭痛
・肩こり
これらの症状は日常生活に影響を与え、運転やコンピューター使用、読書やスポーツなどの余暇活動がより困難になることがあります。
病的な乱視
普通の乱視は、生まれつきの乱視や、それに年齢的な変化が加わった乱視で、これらは、眼鏡に少し乱視のレンズを加えることで十分な視力を得ることが出来ます。しかし、時に「病的な乱視」もあります。病気によって引き起こされている乱視や、眼鏡では矯正しきれない程の強い乱視です。病的乱視を引き起こすものとして、
• 円錐角膜(角膜が前方に突出してくる病気)
• 翼状片(鼻側の白目が黒目に入ってくる病気)
• 目の手術後、目のケガの後遺症 などです。
また、成人病として有名な「白内障」は水晶体乱視の原因の一つです。これら原因がはっきりしている時は、その原因治療ができれば乱視を治すことが出来ることになります。
例えば、白内障によって、強い水晶体乱視が発生しているときは、白内障の手術をすることで治せます。また、白内障手術が原因で強い角膜乱視になっている人がいます。これは、白内障手術の傷口の治りの悪い人に起こりやすく、乱視矯正角膜切開術(後述)という手術によって乱視を治すことができます。
「正乱視」と「不正乱視」
基本的に、乱視がない状態は角膜や水晶体の表面が理想的な球面形をしており、歪みがないわけで、角膜がきれいな球面(バスケットボールのような形)をしているため、光は一点に集まり、くっきりと見えます。乱視は、この球面形に歪みがある場合です。歪みといってもいろいろな歪み方がありますが、球面をある一方向からつぶしたような形(ラグビーボール型)に歪んでいる乱視を「正乱視」といい、球面形が不正デコボコになっている歪みを「不正乱視」といいます。一般的には「正乱視」がほとんどで、「不正乱視」は、先に述べた病的な原因によって引き起こされる場合がほとんどです。正乱視は、それが角膜乱視であっても水晶体乱視であっても、眼鏡に乱視を入れることで視力を矯正することができます。一方、不正乱視は眼鏡では矯正できません。角膜の不正乱視は、ハードコンタクトレンズ(後述)でなら矯正できます。水晶体の不正乱視は良い矯正方法がありません。
乱視の検査
乱視は、眼科での総合的な眼科検査によって診断されます。
▶設備案内ページ他覚的屈折検査
オートレフラクトメーター: 機械をのぞき込んで、気球の絵などを見る検査です。眼の屈折度数(近視・遠視・乱視の度数)を客観的に測定します。
- トプコン社「レフトポ」
- ニデック社「トノレフ2」
自覚的屈折検査
検眼枠でレンズを入れ替えながら、「輪っかの空いている方向はどちらですか?」と質問し、最も見やすい度数を調べる検査です。近視遠視の度数、乱視の度数方向(軸)を測定します。
角膜形状測定(角膜表面の曲率測定)
角膜トポグラフィー(角膜表面マップ)乱視の原因が角膜にあるか、どの程度なのかを詳細に評価できます5 。
- トプコン社「レフトポ」
- トプコン社「ウェーブフロントアナライザー」
前眼部三次元画像解析(角膜前後面測定)
- OCULUS社「ペンタカムHR」
- TOMEY社「カシア2」
これらの機器のデータを照合して、あなたの乱視の種類が解ります。みやた眼科では、視力測定の時やコンタクトレンズを合わせるときはもちろんですが、白内障手術の時にも手術前からある乱視を減らすために、これらの装置を利用して手術方法を決めています。場合によっては、白内障手術と乱視を治す手術を同時に行っています。
乱視の矯正・治療
乱視の矯正方法
乱視が視力に影響している場合、乱視を矯正する必要があります。一般的な方法は眼鏡に乱視のレンズ(円柱レンズ)を入れる方法です。レンズに乱視を入れたからといっても外見上普通の眼鏡となんら変わりはありません。ただし、眼鏡に入れられる乱視の量には限界はあります。あまり強い乱視のレンズは、それをかけた時に地面が歪んで(傾いて)見えてしまいます。眼鏡で補えないくらいの強い乱視に対しては、コンタクトレンズを利用するか、手術をして乱視を治すかのどちらかでしょう。以前は乱視眼に対してはソフトコンタクトレンズではやわらかく、角膜の歪みをそのまま再現してしまい矯正しにくいためハードコンタクトレンズが一般的でした。しかし近年では良い乱視用ソフトコンタクトも登場して乱視のタイプによっては矯正が可能です。レンズが眼の中で回転しないように工夫されており、乱視を矯正できます。ワンデータイプも2ウィークタイプもあります。
乱視を治す手術
■LRI(Limbal Relaxing Incision:角膜輪部減張切開術)
角膜の縁(黒目白目の中間くらい)に100分の1ミリの精度で角膜の厚さの90%程度の切り目を入れます。これによって角膜の歪みを補正する事ができます。角膜のどの位置に、どれくらいの深さ、どれくらいの長さの切り目を入れるかは、乱視の量や方向によって決まります。このために上で述べた角膜曲率解析装置が用いられます。全ての乱視が対象となるわけではありませんが、白内障手術時や手術後に残った乱視に対して行うことがあります。
■乱視入り眼内レンズを用いた白内障手術
白内障手術で眼内に移植される眼内レンズに乱視度数を持ったレンズ(トーリック眼内レンズ)が開発されました。このトーリック眼内レンズを白内障手術の際に用いると角膜乱視がある患者さんも良好な視力を得ることができます。
■LASIK(レーシック)
LASIK手術は普通、近視を治すために行われている角膜を削る手術ですが、この手技で乱視を治すことができます。健康保険が適応されない自費診療でやや高額です。病的な乱視は治療できないことがありますので、注意が必要です。
お子様の乱視について
小さなお子様の場合、強い乱視があるとピントの合った鮮明な像を常に見ていないため、視力の発達が妨げられ、「弱視」になってしまうことがあります。弱視は、メガネなどを使っても十分な視力が出ない状態です。早期に発見し、適切にメガネなどで矯正して、視力の発達を促すことが非常に重要です。3歳児健診などの視力検査は必ず受け、気になることがあれば早めに眼科を受診しましょう。特に子供や若年成人では、乱視が時間とともに悪化することがあります。
よくある質問
Q: 乱視は失明につながりますか?
A: いいえ、乱視が失明に直接つながることはありませんが、乱視に関連する特定の疾患や状態が進行すると視力に大きく影響します。
・円錐角膜
円錐角膜は角膜が円錐形に突出する進行性の疾患で、不正乱視の原因となります。重度に進行した場合、角膜が極端に薄くなり、視力が著しく低下します。
・白内障
乱視の原因の一つに水晶体の異常による「水晶体乱視」があります。白内障が進行すると水晶体が濁り、不規則な乱視を引き起こします。白内障を放置すると、ぶどう膜炎や緑内障などの合併症を引き起こし、失明することもあります。
Q: 乱視は自然に治りますか?
A: 基本的に乱視は自然に治ることはありません。眼鏡、コンタクトレンズでの矯正が一般的で、場合よっては手術が検討される場合もあります。
Q: 乱視は時間とともに悪化しますか?
A: どちらともいえません。成長・加齢とともに乱視が悪化する場合もあれば減少する場合もあります。まぶたの圧力や目の生理的な変化によって影響を受けるためです。一般的には幼児期に倒乱視(水平方向のカーブがきつい乱視)が多く見られます。その後、20歳頃までは徐々に直乱視(垂直方向のカーブがきつい乱視)が増加していきます。その後、再び倒乱視が増える傾向が数十年と続くというパターンが多いです。
Q: 乱視はストレスが原因になりますか?
A: いいえ、ストレスは乱視の原因ではありません。しかし、頭痛や眼精疲労などの症状を悪化させる可能性があります。